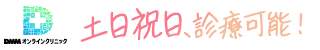「イライラするのは自分のせい?」「生理前になると毎月つらい…」そんなふうに感じたことはありませんか?
PMS(月経前症候群)は、生理前にあらわれる心と体の不調のことです。
人によって症状はさまざまですが、放っておくと日常生活に支障が出ることも…。
今回の記事では、PMSの症状や原因をわかりやすく解説しながら、自分でできるチェック方法や対策まで詳しく紹介します。
PMSとは?まずは基本から確認
生理前になると気分が落ち込んだり、体がだるくなったりすることはありませんか?
それ、もしかするとPMSかもしれません。
PMSの意味と「生理前」の関係
PMSは「Premenstrual Syndrome(プレメンストル・シンドローム)」の略称で、日本語では「月経前症候群」と呼ばれています。
排卵から生理が始まるまでの期間に、心や体にさまざまな不調があらわれるのが特徴です。
イライラや気分の落ち込み、頭痛、吐き気、眠気など、人によって現れ方は異なりますが、生理が始まると自然とおさまるのが共通点といえるでしょう。
つまり、「生理前にだけつらくなる」「毎月決まって同じ時期に不調になる」と感じるなら、PMSを疑ってみる価値があります。
「これってPMS?」セルフチェックリスト
なんとなく不調を感じていても、PMSかどうか判断に迷う人も多いかもしれません。
以下のセルフチェックリストを使って、いくつ当てはまるか確認してみてください。
-
生理前になると、イライラしやすくなる
-
理由もなく落ち込む、涙もろくなる
-
胸が張る、むくむ、頭痛や腹痛が起こる
-
甘いものや炭水化物が無性に食べたくなる
-
集中力が落ちて仕事や家事が手につかない
- 眠気が強い
-
肌荒れやニキビが増える
-
生理が始まると症状が和らぐ
3つ以上当てはまる人は、PMSの可能性があります。気になる人は、生理スケジュール管理アプリや手帳などに体調の変化を書きとめてみるのもおすすめです。
「PMS」と「PMDD」の違いは?
PMSと似た言葉に「PMDD(月経前不快気分障害)」があります。
PMDDはPMSの中でも精神的な症状が強く、日常生活に支障が出るほど深刻な状態を指します。
たとえば、怒りっぽさや無気力、落ち込み、不安感が強くなって、人間関係や仕事に影響するようなケースがこれに当たります。
もし、気持ちの浮き沈みが激しくて苦しいと感じているなら、婦人科で相談してみるとよいでしょう。
PMSの主な症状とは?

PMSでは、心と体にさまざまな不調が現れます。
ここでは、代表的な症状を精神的・身体的・日常生活の3つに分けて紹介します。
精神的な症状:イライラ・不安・落ち込みなど
PMSでよく見られるのが、気分の波や情緒不安定といった精神的な症状です。
-
些細なことでイライラする
-
理由もなく落ち込む
-
急に涙が出る
-
集中力が続かない
-
人との関わりが面倒に感じる
こうした変化は、生理が始まると自然に軽くなるのが特徴です。
自分を責めすぎず、「ホルモンの影響かもしれない」と捉えるだけでも気持ちがラクになるでしょう。
身体的な症状:頭痛・吐き気・むくみ・胸の張り
体の不調もPMSのサインとしてよく知られています。
-
頭が重い・ズキズキする
-
吐き気やめまいがある
-
下腹部や腰が痛む
-
胸が張って触れると痛い
-
顔や足がむくむ
症状の出方には個人差があり、月ごとに軽くなったり強くなったりする人もいます。
日常生活への影響:眠気・集中力の低下・食欲変化
体調や気分の変化が、生活のリズムにも影響を与えることがあります。
-
眠気が強い
-
食欲が増す
-
甘いものを食べたくなる
-
ボーッとして仕事や家事に集中できない
これらの変化は、ホルモンバランスの影響で自律神経が乱れることが原因とされています。
「なんだか調子が出ないな…」と感じるときこそ、無理せず過ごす工夫が大切です。
どんな人がなりやすい?PMSの要因をチェック

PMSは誰にでも起こりうるものですが、なりやすい人にはいくつかの傾向があります。
ここでは体質・生活習慣・妊娠初期との違いについて解説します。
ホルモンバランスの乱れ
PMSの主な原因が、女性ホルモンの変動です。
排卵後から生理までの間、エストロゲンとプロゲステロンという2つのホルモンが大きく変化します。
このホルモンバランスの揺れが、心身の不調を引き起こす要因になると考えられています。
特に、もともとホルモンの影響を受けやすい体質の人や、月経周期が不安定な人は症状が出やすい傾向があります。
ストレスや睡眠不足との関係
ストレスや睡眠不足は、PMSの症状を悪化させる大きな要因です。
ストレスが続くと、自律神経やホルモン分泌のリズムが乱れ、精神的な症状が強く出ることがあります。
また、睡眠不足が続くと体の回復力が下がり、疲労感や頭痛といった身体症状も出やすくなります。
毎日の生活習慣を見直すことが、PMS対策の第一歩といえるでしょう。
妊娠との違いを見分けるポイント
PMSと妊娠初期症状は似ているため、見分けがつきにくいことがあります。
たとえば、胸の張り・吐き気・眠気などはどちらにも見られる共通の症状です。
見分けるポイントのひとつは、症状が生理開始とともにおさまるかどうか。
PMSの場合は生理が始まると症状が軽くなるのに対し、妊娠している場合は予定日になっても生理が始まらずそのまま続くことが多いです。
不安なときは、基礎体温の記録や妊娠検査薬の使用で早めに確認するのもよいでしょう。
PMSの症状とどう付き合う?タイプ別の傾向と対処のヒント

PMSの感じ方は人それぞれ。
ここでは、症状の出方の傾向をタイプ別に見ながら、自分に合った向き合い方を考えてみましょう。
精神的に落ち込みやすいタイプ:言葉や視線に敏感になる傾向
このタイプはHSP気質の人に多く、生理前になると自分を責めたり、周囲の何気ない言葉に過剰に反応してしまう傾向があります。
たとえば、「なんでそんなことで怒ってるの?」という一言が頭から離れなかったり、普段なら流せるSNSの投稿を見て落ち込んだり。
自信を失いやすくなり、「自分はダメな人間なのでは」とネガティブな思考に陥ってしまうこともあります。
こうした時期は、自分の心を守ったり、気分が紛れる選択を意識してみましょう。
-
SNSなど心をざわつかせるものを見ない
-
予定を入れすぎない
- 好きな映画やドラマ、漫画などのエンタメコンテンツを観る
-
やさしい言葉をかけてくれる人とだけ過ごす
ネガティブな感情を無理に消そうとするのではなく、意識を“今ここ”に切り替える工夫が、落ち込みを軽くする手助けになります。
身体の症状が強く出るタイプ:つらさを我慢して動き続ける傾向
頭痛や腹痛、吐き気、だるさなどを抱えていても、「これくらいで休めない」と無理をしがちな人が多いのがこのタイプ。
とくに仕事や家庭の責任を強く感じる人は、「調子が悪い」と声に出すことに罪悪感を持つことがあります。
ですが、PMSの身体的な症状は睡眠や血行不良、冷えが重なるとさらに悪化しやすいのが特徴です。
対処のポイントは、「早めに緩める」こと。
- 足、お腹を温める
-
思い切って人に頼る
-
休む・寝る時間を確保する
-
カフェインを控える
-
湯船に浸かって血流を促す
「明日の自分を守るために、今日は緩めておく」そんな意識が、つらさを溜め込まないコツです。
気づかれにくい“隠れタイプ”:食欲や眠気の変化がヒントになる
「自分はPMSじゃないと思っていたのに…」という人に多いのが、眠気や過食といった“非典型的な症状”です。
このタイプは、心や体の不調としては出にくい代わりに、以下のような行動が現れやすくなります。
-
甘いものを食べたくなる
-
食べてもすぐに空腹を感じる
-
寝ても寝ても眠たい
-
仕事や勉強に集中できない
-
つい買い物で気を紛らわせようとする
周囲からは「だらけている」と見られてしまうこともありますが、実際はホルモンによる脳の疲労や血糖値の急変動が背景にあることも。
対処としては、血糖値の急上昇を防ぐ食事を意識するのが効果的です。
-
朝食を抜かない
-
白米や甘いお菓子を控え、たんぱく質や食物繊維を多めにとる
-
食事の順番を「野菜→たんぱく質→炭水化物」にする
「気分の変化はなくても、体のサインは出ている」ことに気づくことで、対策のヒントが見えてくるでしょう。
PMSの対策方法|つらい時のセルフケア

PMSとうまく付き合うには、症状がつらくなる前に「緩やかに整える」ことが大切です。
ここでは、生活習慣の見直しから市販薬・サプリメントまで、自分でできるケアの方法を紹介します。
食事・運動・睡眠のリズムを整える
まず見直したいのが、毎日の生活リズムです。不規則な生活はホルモンバランスを乱しやすく、PMS症状を悪化させる要因となります。
とくに意識したいポイントは次の3つです。
-
食事:甘いものや脂っこい食事を控え、鉄分・カルシウム・ビタミンB6などを意識して摂る
-
運動:ストレッチや軽いウォーキングでも十分。血流が良くなると、むくみやだるさの軽減につながる
-
睡眠:睡眠不足は自律神経の乱れや情緒不安定につながりやすいため、なるべく同じ時間に就寝・起床を心がける
難しいことを一度に始める必要はありません。「夜はスマホを見ずに眠る」「白米のかわりに玄米にする」など、小さな習慣を積み重ねていくことが大切です。
サプリメント・漢方の活用方法
市販のサプリメントや漢方薬も、PMS対策として取り入れやすい手段です。体質に合うものを選べば、穏やかに症状を整えるサポートになります。
【サプリメント】
- ビタミンB6・マグネシウム: 精神的な不調(イライラなど)の緩和が期待され、セロトニン生成もサポートします。
- カルシウム: 神経の過敏さや精神症状の軽減に役立つ可能性があります。
- 鉄分: PMS時の疲れやすさや倦怠感の軽減につながることがあり、特に生理量が多い方におすすめです。
【漢方薬】
- 命の母ホワイト・当帰芍薬散など: PMS対策に特化した漢方薬として知られ、症状や体質に合わせて選べます。
- 体質に合わせた漢方の選び方: 冷え性、イライラ、むくみなど、個々の体質に合わせて漢方薬を選び、根本的なバランスを整えます。
漢方は、冷え性・のぼせ・疲れやすさなど、自分の体質ごとに選ぶことができる点がメリットです。
「なんとなく不調だけど、病院に行くほどでも…」というときの選択肢として取り入れてみるのもよいでしょう。
市販薬を使うときの注意点
PMSがつらいとき、市販薬に頼るのもひとつの方法です。痛み止めや鎮静作用のある薬は、症状を一時的に和らげてくれます。
ただし、薬で無理にがんばり続けてしまうと、根本的な改善にはつながりません。
使用する場合は、「今週だけ乗り切りたい」「大事な予定があるから」など、目的を明確にしたうえで活用するのがおすすめです。
また、自己判断で複数の薬を併用すると副作用のリスクもあるため、添付文書をよく読み、できれば薬剤師に相談してから使うと安心です。
それでもつらい時は?病院で相談する目安

セルフケアを続けても改善が見られない場合や、日常生活に支障をきたすほどつらい場合は、婦人科での相談を検討してみてください。
専門的な診断と治療を受けることで、症状が大きく軽減するケースもあります。
受診を検討すべき症状とは
以下のような症状がある場合は、一度婦人科を受診するのが安心です。
-
気分の落ち込みが強く、何も手につかない
-
家族や職場の人に当たってしまい、自己嫌悪が続く
-
毎月、決まった時期に頭痛や吐き気で動けなくなる
-
生理前の症状が月を追うごとに重くなっている
PMSは個人差が大きいため、「つらいけれど相談するほどではないかも」と我慢してしまう人も多いですが、生活に支障が出ている時点で“相談する理由”は十分にあると言えるでしょう。
診断や治療の流れ
婦人科ではまず、月経周期や症状のタイミング、強さなどについての問診が行われます。
そのうえで、PMSかPMDDか、あるいは他の病気の可能性があるかを見極めていきます。
治療の選択肢は以下のように複数あります。
-
低用量ピルによるホルモンバランスの調整
-
漢方薬や抗不安薬などの投薬治療
-
生活指導やカウンセリングを取り入れた総合的なケア
症状の重さや体質に合わせて提案されるため、「話を聞いてもらうだけでも気がラクになった」という人も少なくありません。
PMS診断に使われるチェック表とは
病院での診断には、「PMSスコア」や「症状記録表」といったチェックリストが使われることがあります。
これは、生理周期と症状の関係を見える化するためのもので、受診前に自分で1〜2ヶ月分自分で症状をメモしておくとスムーズに診察が進みます。
スマホの生理管理アプリでも、体調や気分を日ごとに記録できるものがあります。
気になる症状がある人は、今日から記録を始めてみるとよいでしょう。
よくある疑問|Q&A

ここでは、PMSにまつわるよくある疑問について、安心して読み進められるよう丁寧にお答えします。
Q.PMSはいつからいつまで続くの?
A.一般的に、PMSの症状は排卵後(生理の約2週間前)から始まり、生理が始まるとおさまることが多いとされています。
ただし、個人差が大きく、「生理開始後も数日続く」という人もいれば、「排卵直後から不調になる」というケースもあります。
症状が出る時期や持続時間を把握するためには、自分の月経周期を記録することが効果的です。
Q. PMSと妊娠初期症状の違いは?
A.PMSと妊娠初期の症状は非常によく似ています。たとえば、以下のような共通点があります。
-
胸の張り
-
眠気やだるさ
-
食欲の変化
-
気分のムラやイライラ
違いの一例としては、PMSの場合は生理が始まると症状が軽くなるのに対し、妊娠している場合は症状が続く、あるいは強くなる傾向がある点です。
不安なときは、基礎体温の記録や妊娠検査薬を使って早めに確認すると安心です。
Q. 年齢によってPMSは変化する?
A.はい、PMSは加齢とともに変化することがあります。
20代では精神的な不調が中心だったのが、30代以降は身体的な症状が強く出るようになることも。
また、出産経験や更年期の影響で症状が軽くなる人もいれば、逆に悪化する人もいます。
体の変化とともにPMSの出方も変わっていくため、「以前とは違う不調を感じる」ときは、あらためて記録をとり直してみるとよいでしょう。
Q.更年期障害との違いや関係はある?
A.PMSと更年期障害はどちらもホルモンの変動によって起こるため、似たような症状が出ることがあります。
とくに30代後半〜40代にかけては、PMSと更年期の症状が重なる「移行期」にあたる人も少なくありません。
更年期障害では以下のような症状が見られます。
-
急なほてり(ホットフラッシュ)や発汗
-
頻繁なイライラや気分の落ち込み
-
睡眠の質が悪くなる
-
月経周期の乱れ
一方、PMSは生理前にだけ周期的に出るという点が特徴です。「月経周期が安定していたのに乱れ始めた」「症状が以前より強くなった」と感じる場合は、PMSだけでなく更年期の始まりサインかもしれません。
心配なときは婦人科でホルモン値を測ってもらうこともできます。早めの相談が、体と気持ちをラクにする第一歩です。
まとめ|気になる不調は我慢せず、早めにケアを

PMSは、つい「気のせい」「がまんすればいい」と思われがちですが、心や体からの大切なサインです。
症状の出方は人それぞれで、精神的に落ち込むタイプもいれば、体に不調が出るタイプ、あるいは自覚しにくい“隠れタイプ”の人もいます。
だからこそ、自分のパターンに気づいて、無理なく向き合っていくことが大切です。
生活習慣の見直しやセルフケアを通じて少しずつラクになることもあれば、病院での相談でぐっと気持ちが軽くなることもあります。
「いつもと違う」と感じたときは、自分を責めず、まずはゆるやかにケアしてみてください。
小さな気づきが、次の生理前の自分をきっと助けてくれます。